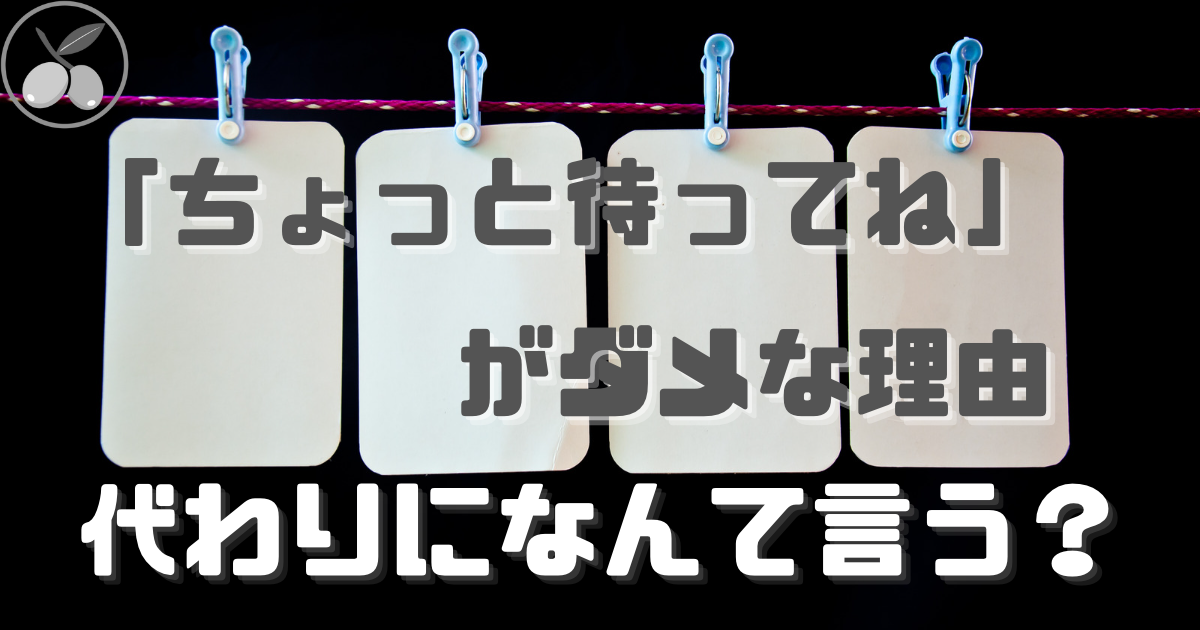「待つ」子育ての重要性については、さまざまな育児書、幼児教育で唱えられています。
月に1度のベビー公文では大きく5つのテーマに分かれて子供への接し方が出されていますが、そのうちの1つが「待つ」になっています。
待つことが大事と頭でわかっていても、仕事と家事に追われるとなかなか快く待ってあげられないことが…。
ワーママVS待つこと
心に余裕を持って待つことがなにより難しい。
朝の出勤前は特に時間に追われてしまいます。
長女は2歳あたりから、私が出した服も「今日はこれじゃない。」と選び直すようになりました。
おまけに出かける直前、おもちゃを出して遊び始める、外に出ると周りの鳥、虫、花に興味を持って遊び始める、、、。
自我の芽生えと共に親の思うどおりにコントロールするのは難しく、一筋縄ではいかないようになりました。
待つことが苦手…解決策は!?
時間に余裕を持って行動。一択です。
繁忙期は特に、時間への焦りと物事が思い通りに進まない事にイライラしていましたが、イライラした気持ちで接したことに出社してから後悔することがありました。
それからわが家は朝方に切り替えました。
10分〜15分早く行動すれば大体のイライラは解消されます。
子供が自分で靴を履こう、服を着よう。と頑張る姿も優しく見守ることができます。
かかる時間はその子それぞれで違います。靴を履くのに5分もかかる。なんて大人の感覚から思ってしまいがちですが、、、ぐっとこらえましょう。
成長の証です。
前もって行動しても、うまく行かないことは勿論あります。
1,2歳のまだ物事を理解できない子供に「ママ、会社遅刻しちゃうから急いで。」と言ってもピンとくるはずありません。
それよりも、自分で靴を履こうとしている姿、着替えをする姿の方が子どもにとっては大きな挑戦です。
阻害することなく暖かく見守ってあげることで、自信と達成感を感じることができる良い機会ですので、大人事情に振り回さないようにしましょう。
TPOにもよりますが、ちょっと遅刻していくなど、子供優先にすることも時には必要だと思います。
一生続く訳ではないですし、心の発達・脳の発達が著しいこの時期に、大人都合のストレスを与える事はあまり良いとは思えません。
手を出さないで待つ
1人で一生懸命頑張っていることは手を出さずに見守ります。
ボタンかけ、着替え、パズルなどの遊び。
怪我や事故を防ぐために目は離さないようにしますが、基本手は出さずやりたいようにやらせてあげます。
中には、「あぁ。部屋が散らかる。洗濯が大変。」なんて思うような事もあります。
わが家は部屋中、小麦粉だらけになったこともありました。
しかし、集中して夢中になって遊んでいるということは、それほど頭を使い考え、感じ取っていることにつながります。
応援する・助言する
くじけそうになったら、手は出さず応援してあげます。
「頑張れー。もう少しでできるよ。〇〇ならできるよ!」と声をかけてあげると、本当にそのとおり出来るようになります。
言葉の力は凄いです。
また、諦めそうになったときは、助言してあげます。
パズルができない時は「この青いピースやってみたら?」など。答えを自然と手元においてあげて成功体験を増やします。
2歳7ヶ月あたりから、言葉で助言したことに対して、「これのこと?こーでいいの?」なんて返答も返ってくるようになりました。
勿論、成長を「待つ」事も大事です。周りと比べない。
親となり、一番の課題は待つ事なような気がします。
他にも様々な「待つ」形が。。
また追って、書いていきたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございます。